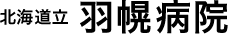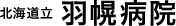広報はぼろ2025年7月号掲載のコラム記事
先月は熱中症対策として「暑熱順化」という体の準備の話をしましたが、今回は熱中症になりやすい環境、特に盲点となりやすい環境について、また熱中症対策や発症時の対応をお伝えします。
熱中症は、高温の環境下、つまり屋外の炎天下での発症が典型です。しかし、次のような意外な環境にも注意が必要です。1つ目は「室内」です。冷房がない、もしくは節電で控えめに設定された部屋で、湿度が高い場合は特に危険です。厨房のような火を使う場所はもちろん熱くなります。特に高齢者は温度の変化に気づきにくいため要注意です。2つ目は「夜間」です。寝ている間も気温が下がらない場合、寝汗で脱水が進んでいるケースがあります。寝付く時にクーラーをかけて、タイマーで消す設定にする場合、閉め切った室内では室温が上昇してしまいます。3つ目は「車内」です。エンジンを切って駐車中の車内にいるのは非常に危険です。わずか10分でも車内温度は急上昇します。子供の悲惨な事故は毎年報道され心が痛みます。
熱中症は早めに気づくことや対策が重要です。まず温湿度計は必ず室内には設置しましょう。室温だけではなく湿度も重要で、70%以上では発汗されにくく、体温調整の妨げになります。一般の方にはなじみがないですが、熱中症は「暑さ指数(WBGT)」が指標となります。5,000円程度で測定器が販売されているので、用意できるならこれがベストです。
塩分や水分の摂取には気を配りましょう。特に子供は無理をしがちです。遊んだりスポーツをしている子供は、楽しいことが最優先ですので、大人が声掛けしなければ水分を摂りません。部活動やスポーツ少年団などはもちろん、家族で遊ぶときでも注意しましょう。最近は「塩分タブレット」をよく見かけるようになりました。適宜塩分補給をすることも有効です。衣類や寝具では、薄手のものや通気性の良いものを使用し、首元の開いた服の方が熱気が逃げていくためよいでしょう。冷感素材を用いたものが増えていますが、特に寝苦しい夜のような調整が難しい時間帯には特に活用したいところです。
症状は、立ちくらみ、めまい程度で軽く済むようであれば、冷やして経過観察で構いませんが、頭痛や吐き気、意識がぼんやりするような状況では医療機関の受診が好ましいです。意識障害があり、呼吸も乱れたり痙攣する状況は救急車をすぐに呼びましょう。医療機関受診までに、衣類を緩め体を冷やすこと、特に首の付け根や脇の下、股関節など太い血管がある場所を冷やすことは、体温を下げやすくします。自宅でも外出時でも保冷剤を用意して備えておくと良いですね。