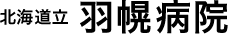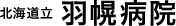広報はぼろ2025年8月号掲載のコラム記事
熱中症以外にも気温や湿度、生活スタイルの変化により引き起こされる“夏特有”の症状や疾患がいくつも存在します。夏は残りわずかになりましたが触れておきたいと思います。
高温多湿の夏は食中毒、特に細菌性のものがピークとなります。特に注意が必要なのは、調理後に常温で放置されたお弁当や惣菜などです。細菌にとってベストな温度が30℃台後半で、反対に低温には弱いとされています。調理済みのものは冷蔵で保存するようにしましょう。ただ、なんでもすぐに冷蔵庫に入れてしまって良いわけではありません。しっかり粗熱をとってからにします。特にカレーを作って鍋のまますぐに冷蔵庫にしまうと、内部が冷めないままになります。小分けにしたり、外から冷やしながらかき混ぜるなどして、2時間程度で冷まして冷蔵庫に入れましょう。また冷やしたものを食べるときは、しっかり再加熱することも重要です。手足や口に水脹れのような発疹ができる手足口病は去年の夏に流行し、例年7月から8月にかけて流行します。そのほかにも夏風邪のウイルスなどありますが、なかなか防ぎようがありません。症状がある時は休むことが流行を最小限にします。
汗を多くかくため皮膚トラブルも増える時期です。汗の塩分や皮脂が肌に残ると、汗疹や肌荒れを起こしますので、通気性の良い服を着たり、こまめに汗を拭く、シャワーを浴びるなどしましょう。
半袖や短パンなど肌の露出の多い服を着ると気になるのは虫刺されです。特に蚊やダニ、蜂の活動が活発になります。蚊やダニに刺されるとウイルス感染症を起こすことがあり、最近ではマダニに刺されることで命に関わる感染症のニュースをよく見かけます。蜂刺されはアナフィラキシーを起こすことがあり、刺されてから数分で呼吸困難や意識障害が見られる場合があります。この場合は速やかに救急車を呼ぶ必要があります。過去に起こしたことがある場合は、エピペン(アドレナリン自己注射)を保有して出かけるようにし、持っている場合は期限が切れていないか確認しておきましょう。
夏は気分が乱れる方が多くいます。「夏バテ」もその一つですが、自律神経が乱れやすく、空調の効いた室内と暑い室外の気温差、日照時間が長いことで睡眠リズムが整わなくなるなどします。明るいからと早朝に起き出して日光を浴びてしまうと、先々に不眠につながっていくこともあります。明るさではなく、時間で行動するように心がけておきましょう。
夏休み期間は、子供もその世話をしている大人も、楽しい時間には体調不良を感じにくく、その負荷を後から感じることもあります。普段から適度に休息を取るようにして、疲れを残さないようにしておきましょう。