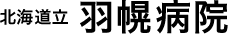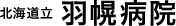広報はぼろ2025年10月号掲載のコラム記事
今年度の健診を終えられた方が増え、最近はその健診異常での精密検査での受診が増えています。健診で指摘される項目の中で多いものの1つとして「肝機能障害」があります。その原因として最も多いものが「脂肪肝」です。脂肪肝に至る理由として、アルコールを飲む方のみならず、飲まない方においても脂肪肝が生じます。脂肪肝とは、肝臓に中性脂肪が過剰に溜まった状態で、多くの方で自覚症状がありませんが、炎症が進むと肝臓の細胞が傷つけられてしまうことで、肝硬変や肝臓がんに進んでいくこともあります。
従来、そのような非飲酒者の脂肪肝を「NAFLD(ナッフルド):非アルコール性脂肪性肝疾患」と呼称してきました。しかし、この英語名には「肥満(Fat)」という単語を含んでいること(日本語訳では「脂肪」と置き換えています)、高血圧や糖尿病、脂質異常といったメタボリックシンドロームが強く関係していることが明らかになったことから、「MASLD(マッスルド):代謝機能障害関連脂肪性肝疾患」と名称が変更になりました。
脂肪肝の最大の原因は、エネルギーの摂り過ぎと運動不足による内臓脂肪の蓄積です。そこに糖尿病や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病が複雑に絡み合い悪循環を生みます。例えば、糖尿病患者では半数以上に脂肪肝を合併し、脂肪肝の患者は健康な人に比べて2倍以上糖尿病になりやすいとされます。糖尿病・脂肪肝のそれぞれが、血糖を下げるインスリンが効きにくくなること、慢性的な炎症が生じることが、相互に関係すると考えられています。わが国の糖尿病患者さんの死因において約1割が肝疾患(肝硬変や肝臓がん)とされています。ですので、脂肪肝とはいえ侮れないのです。
脂肪肝を治療できる薬剤として承認されている薬剤は現時点ではありません。糖尿病の治療薬が肝臓の炎症を改善させ、数値を改善させるという報告は見られていますが、「糖尿病」という診断がされている方にしか用いることができません。薬以外でできる有効性が示されていることは、「体重を減らすこと」です。具体的には、体重を5〜10%減量することです。3%〜5%程度でも肝臓の数値はある程度改善しますが、肝臓自体の炎症は継続しています。7%以上減量できた場合、肝臓の炎症も軽減させることができます。
脂肪肝は周囲にもよくいるため油断しがちですが、血液検査値の異常が持続している場合、特に糖尿病患者さんでは肝硬変や肝臓癌に繋がり予後に影響する場合があります。定期的にCTやMRIを撮影したり、血液検査でも肝臓の状態がわかるようになってきていますので、定期受診の際に医師に確認してみましょう。