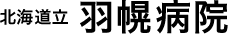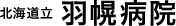広報はぼろ2025年11月号掲載のコラム記事
病気に対する治療を科学的根拠(エビデンス)に基づいて行えるようにするため、「診療ガイドライン」というものが示されることがあります。これにより、患者さんがどこで診療を受けても一定水準の医療が提供されることにも繋がります。今年、日本高血圧学会により「高血圧」のガイドラインが2019年以来6年ぶりに改訂されました。この改訂では、従来の「治療」に加えて、「管理」も重視され、生活全体の見直し、生活習慣や行動を変えていくことも示されています。
一番話題となっているのが、高血圧の目標値が変わったということです。従来は年齢や病気などにより目標血圧が決められていましたが、今回の改訂を機に目標血圧は全年齢で統一することとなり、家庭では「125/75mmHg未満」、診察室では「130/80mmHg未満」を目指すこととなりました。これまでは、75歳以上の高齢者は緩めの基準とされていましたが、年齢関係なく、この目標を満たすことにより心臓や脳の病気の危険を下げることを狙っているそうです。これまでの研究により、血圧管理目標を達成している患者の割合は最大でも約50%に留まることが報告されています。また、目標達成者のうち、使用薬剤数が3種類以上に及ぶケースは全体の約40%に達するとされています。 今回目標血圧が厳格化されたことにより、治療を強化しなければならない方が増えることになります。
新たな薬剤も出てくるなど、治療強化のための薬剤の選択肢は拡がっていますが、何より重要なことは生活習慣の改善です。従来言われている通り、「減塩(体に入る塩を減らす)」、「カリウムの摂取(体の塩分を外に出しやすくする):野菜を多く摂る」、体重管理、運動などの生活習慣の改善が重要であることも示されています。スマホのアプリで血圧を管理することもできるなど、デジタルの活用も治療継続に有効とされています。
自身で生活習慣を改善しても、それが正しいのか患者さんにはわかりにくいものです。羽幌病院では尿検査で「1日塩分摂取量」の推計値を出すことを2013年から行っていますが、今回のガイドラインでは「尿中ナトリウム/カリウム比」の評価が取り入れられ、より食生活の改善効果を確認することができます。羽幌病院でも検査できる項目ですので、今後患者さんの皆さんにもお示しできるようになっていくことと思います。
このガイドラインには、一般の方向けにわかりやすくまとめた「『高血圧』の10のファクト」というものが示されています。ただ、転載することは許可が必要など煩雑で、こちらでは紹介しませんが、ネット検索で閲覧できますので、参考にしてみると良いでしょう。